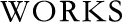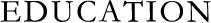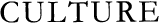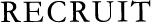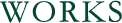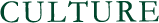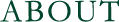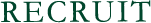#1
金融機関の利用者ニーズも大きく様変わりし、
金融取引をPCやスマホで済ませる人が増えている。
『JAバンクアプリ』の開発担当として配属以来、一貫してその任に当たってきた佐藤ですが、前部署の福岡支店では、福岡県内にあるJAの信用事業を支援、サポートする推進業務に従事していました。それだけに佐藤には、業務を通じて思うところがあったようです。
「デジタルイノベーションの進展によって、金融機関の利用者ニーズも大きく様変わりし、口座の残高照会や振込といった日常的、定型的な金融取引は、PCやスマホで済ませる人が増えていました。こうした変化を受けて他行では、定期預金の預け入れ、住宅ローンの借り入れや繰り上げ返済、税金や公共料金の支払いなど、インターネットバンキングやモバイルアプリバンキングの機能を拡充していましたし、FinTech企業と連携して、家計簿アプリなどの新しいサービスも生み出していました。対してJAバンクはと言えば、インターネットバンキングの利便性向上も道半ばなら、モバイルアプリに至っては提供ができていない状態。これは何とかしなければいけないと、ずっと思っていました」
もちろん、それが無為無策によってもたらされた事態でないことは、佐藤も十分に承知していました。日本全国、津々浦々にまで店舗網を張り巡らし、過疎化や高齢化が進む地域にもしっかりと根を張るJAバンクだからこそ、非対面ではなく対面サービスにこだわってきたからです。それがJAバンクの存在意義であり存在価値のひとつ。この点については佐藤自身、支店という現場にいたからこそ、肌身に染みて理解していました。
しかし、このまま非対面サービスを強化せず、そこで生み出される顧客接点を取り逃がすのはあまりにももったいない。JAバンクのお客様は農家だけでなく、都市部で暮らす勤労世帯の人たちもいる。こうした人たちのニーズを満たせなければ、せっかくのお客様もJAバンクから離れていってしまう——。そう思った佐藤は、次の異動についてはインターネットバンキングに関わる業務を希望していました。そして晴れて配属されたのがJAバンク業務革新部であり、アサインされたのがモバイルアプリ開発でした。
佐藤が着任したのは、『JAバンクアプリ』のプロジェクトが経営会議で承認され、いざ要件定義というタイミングでした。それだけに佐藤はかねてより抱いていた、ある決意にも似た思いを胸に業務に就いたのです。
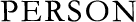 農林中金の人
農林中金の人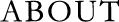 農林中金を知る
農林中金を知る 農林中金が
農林中金が Organization組織概要
Organization組織概要 Recruit site for new graduate
Recruit site for new graduate