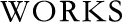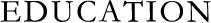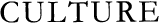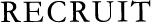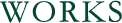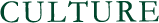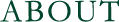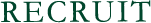#1
クローズドなマーケットのなかで
限られた人たちのもとに実行されてきた不動産投資。
農林中央金庫は「国際分散投資」という投資コンセプトのもとに、約60兆円の資金をさまざまな国々の、さまざまなアセットクラスで運用しています。その投資先のひとつとして国内外の不動産に投資を始めたのは1990年代後半頃から。それは現在のような不動産の証券化マーケットが成熟する以前のことでした。以来、足掛け20年。この間に蓄積されたノウハウ、構築された各プレイヤーとのリレーションシップは、機関投資家としては世界トップクラス。それはそのまま、農林中央金庫の最大の強みとなっています。
それというのも不動産投資というのは、ある特定の不動産の賃料収入を当てにして投資を行うスタイルのため、クローズドなマーケットのなかで限られた人たちのもとに実行されるものだからです。国債や株式のように、発行体である国や会社の信用力を背景にしたオープンなマーケットで、不特定多数の人たちが投資をするのとは対照的です。
不動産投資の場合、その不動産の価値や競争力に案件の一つひとつが支配されるため、個別の案件分析の仕方も特徴的で、伊藤の言葉を借りれば「商品性自体がすごくニッチな領域」。このため不動産投資は、ノウハウの蓄積による高度な専門性と、リレーションシップに基づく信頼関係や協力体制なくしては、すぐに実行できないものなのです。さらに伊藤は次のように指摘します。
「不動産の利回りはキャップレートと呼ばれるのですが、このキャップレートというのは、景気の浮き沈みによって上がったり下がったりを繰り返します。リーマンショックのときには不動産価格も3割くらい下落をして、当庫も損失を出したりしたのですが、そういう景気変動の波にさらされやすいアセットであるというのも不動産の大きな特徴です。この点で、失敗に対するレッスンラーンも極めて重要で、それを地道に20年間積み上げてきた実績が今、農林中央金庫に対する信頼や期待となって、各企業から多くの相談が寄せられる大きな要因となっています」
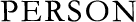 農林中金の人
農林中金の人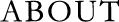 農林中金を知る
農林中金を知る 農林中金が
農林中金が Organization組織概要
Organization組織概要 Recruit site for new graduate
Recruit site for new graduate