01
私たち農林中央金庫が、中途採用を強化する理由
- Q.現状、そして今後のビジネス環境について、どのように認識されていますか?
- 金融機関を取り巻く環境は大変厳しくなっています。グローバルな利ザヤ縮小は言うに及ばず、デジタル化の急速な進展にともなう他業種、他業態の参入によって、競争も激化するばかりです。一方で、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」をはじめ社会の持続可能性に向けた意識が向上し、企業に対する社会的課題解決への期待も高まっています。そして何より、農林中央金庫の存在意義に深く関わる農林水産業においても、担い手の高齢化、規模拡大のニーズ、アジアの成長の取り込みなど、難しい課題が山積しています。こうした実情を踏まえ、これから先の10年を見通したとき、私たちはこれまでに経験してきた変化とはまったく異なる、「非連続な変化」が起こるものと想定しています。
- Q.そのような厳しい状況のなかで、どのように対処しようとしていますか?
- 私たち農林中央金庫は、こうした変化を追い風ととらえ、新たな価値創造へ挑戦するため、2019年度より5ヶ年の中期経営計画に取り組んでいます。実践体制として、すでに4本部制を導入しており、「食農法人営業本部」「リテール事業本部」「GI(グローバル・インベストメンツ)本部」の3本部と、これらを支える「コーポレート本部」の計4本部において、それぞれの計画を実行しています。
- Q.各本部で実行されている計画の概要について、教えてください。
- まず「食農法人営業本部」においては、農林水産業の生産者団体であるJA・JF・JForestを基盤とする強みを活かし、人口の増大や富裕化による食の多様化が進むアジアに向けて食のバリューチェーンを強固につなぐことでファイナンス・ビジネスを創出していきます。国内では、AgTechの発展や生産者の法人化の流れを捉え、シードマネーの供給など経営課題へのソリューション提供によって、生産者所得の向上を実現していきます。
また、「リテール事業本部」においては、JAバンクなどを通じて貸出を強化することで収益向上を図るだけでなく、利用者の皆様の生活ニーズをベースにおいた提案を進めるライフプランサポートの実践、またデジタルイノベーションを活用し、それを契機にした組合員・利用者接点の再構築にも取り組んでいます。
「GI本部」においては、国内最大規模の機関投資家として、グローバルに幅広い市場・資産に分散投資を行っていますが、海外拠点の拡充による案件ソーシング力の強化や、投資手法の進化を図ることで基礎収益力のさらなる向上を図っています。そして「コーポレート本部」においては、部門をまたぐ策として、デジタルイノベーションを推し進めるとともに、従来の業務フローを見直す業務革新にも取り組み、持続可能な財務基盤の構築に力を注いでいます。同時に担当役員のもと、CFT(クロス・ファンクション・チーム)を複数立ち上げ、各本部横断のミッションを推し進めることで、組織全体のさらなるパフォーマンス向上にも取り組んでいます。
- Q.組織をあげて、大きく変わろうとしているわけですね?
- そのとおりです。2019年度からの中期経営計画の最終年度は、農林中央金庫が創設されて100年という大きな節目でもあります。それだけに私たちも、この5年間がその先の100年を大きく左右する大事な正念場であると考えており、役員以下、全職員が緊張感をもって業務にあたっています。とりわけ、先ほど申し上げた「非連続な変化」のなかで、新たな価値創造に挑戦するためには、従前以上に新しい視点や発想力、あるいは高い専門知識が必要であり、さまざまな経歴、知見を備える人材が必要であると考えています。私たちは今こそ、そうした人材を仲間として迎え入れることで、お客様が求めるニーズに沿ったソリューションや商品を提供していきたいと思索しています。そして人材のダイバーシティを推し進めることで、組織の活性化、イノベーティブな効果を生み出していきたいと願っています。これこそ、農林中央金庫が中途採用を強化する理由でもあります。


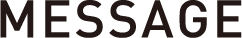 人事メッセージ
人事メッセージ


