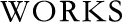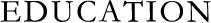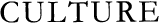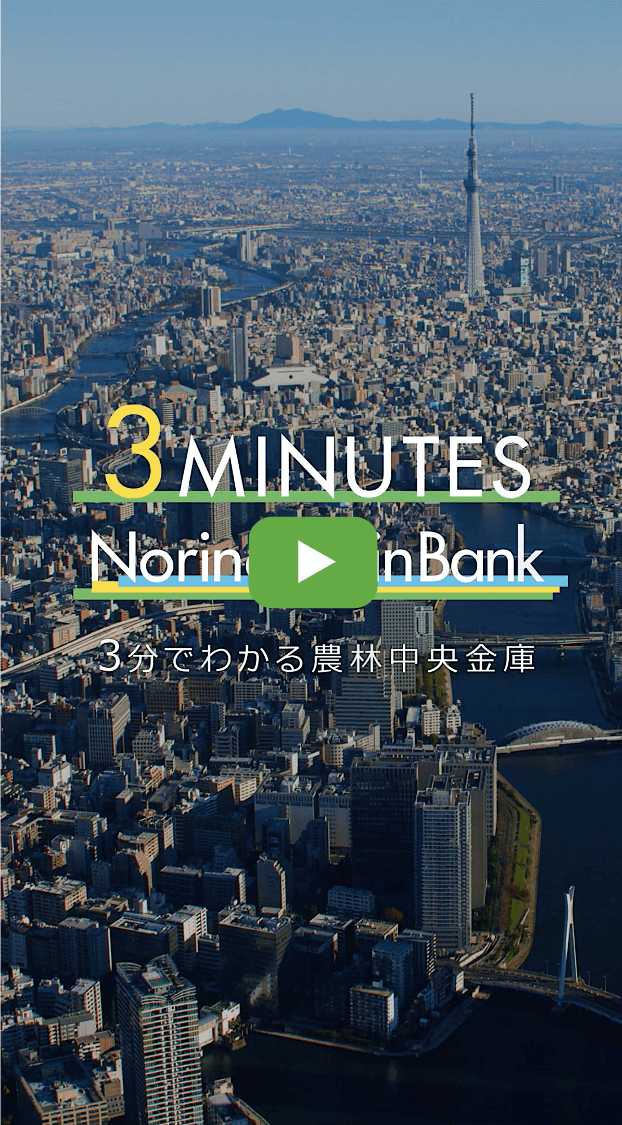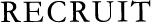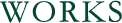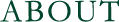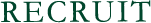これは当県固有の事情だと思いますが、長崎県のJAにはお客様である組合員や利用者のところへ直接出向いて商品提案をする、渉外担当者が存在しません。渉外担当がいないなかで、どうやって実績を上げていくかといえば、窓口担当の方々にやっていただくしかありませんので、少ない人数でも効果的・効率的に数字を伸ばしていける金融商品を選択し、集中的にリソースを投下する、「選択と集中」が非常に重要になってきます。
この観点から力を入れていることの一つが、年金口座の獲得です。年金は個人貯金のなかでもアプローチの効果が比較的出やすい領域のため、我々からJAに潜在顧客のリストを提供するとともに、推進資材としてお客様へのプレゼント企画を用意しています。さらに、JA職員がお客様にどの程度までご案内できたかを確認するための管理ツールを作成し、そのPDCAを回すことにより、施策自体のブラッシュアップも図りながら、職員の皆さんの提案スキル向上と業績アップを支援しています。
また、長崎県は五島や壱岐、対馬などの離島が多く、人が移動することについてのハードルが高いという特徴もあります。この点を考慮し、積極的に活用すべきと考えているのが非対面チャネルです。特に若い世代ではインターネットでの申し込みが普及していますので、マイカーローンを中心とした小口ローンの推進に関しては、非対面チャネルの拡大を目指して、県域を対象としたJAバンクのWeb CM投下に予算を割いています。ここでは当然、PR効果の高い媒体を選択することが重要になってきます。そこでYouTubeやTVerなどのメディアごとに放映後の効果測定を行って媒体を絞り込み、CMからホームページへのリンクにも工夫することで、JA職員が手をかけずとも実績を伸ばせる手法の確立を目指しています。
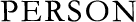 農林中金の人
農林中金の人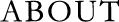 農林中金を知る
農林中金を知る 農林中金が
農林中金が Organization組織概要
Organization組織概要 Recruit site for new graduate
Recruit site for new graduate