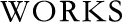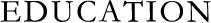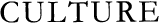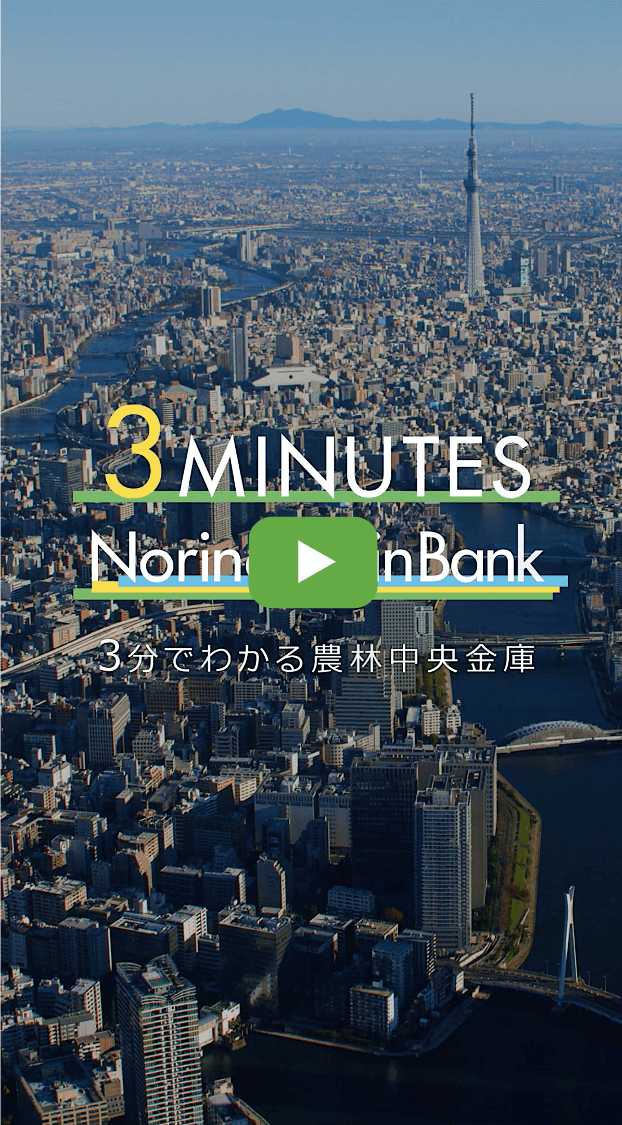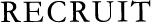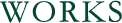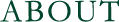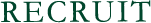- 農林中金の事業
- 農林中金の人
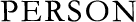 農林中金の人
農林中金の人 - 農林中金で育つ
- 農林中金で働く
- 農林中金を知る
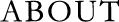 農林中金を知る
農林中金を知る-
 農林中金が
農林中金が
大切にしていること -
3分でわかる
農林中央金庫 -
 Organization組織概要
Organization組織概要
-
- 採用情報
 Recruit site for new graduate
Recruit site for new graduate