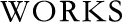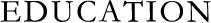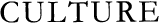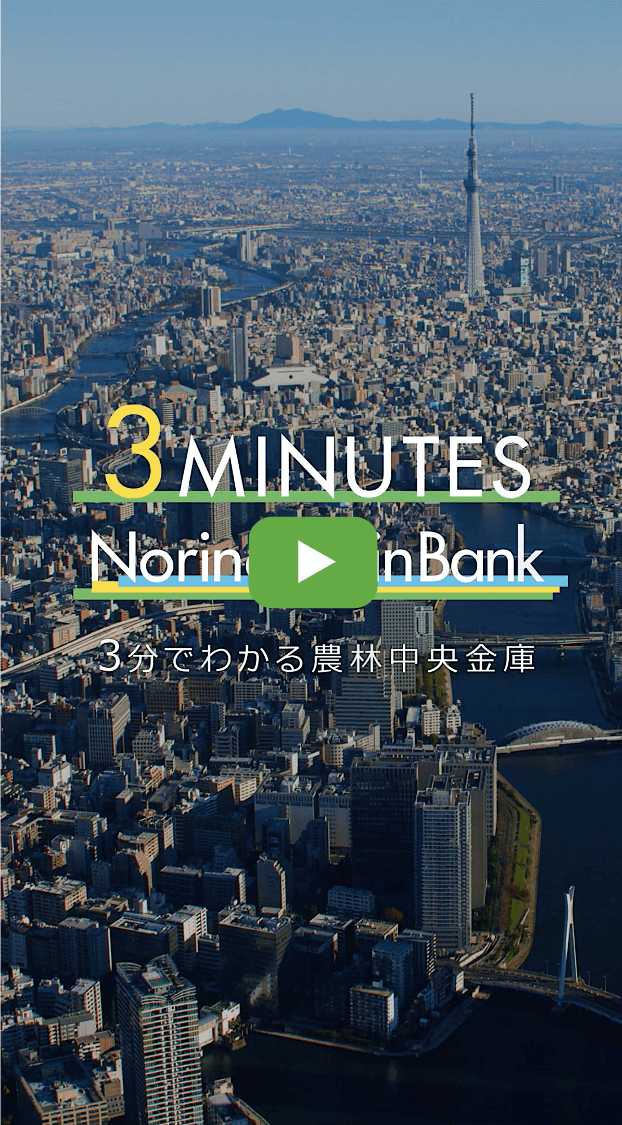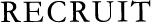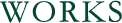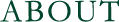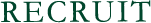農林中央金庫とJAグループが利用するシステムの企画・開発やリスク管理などを行っています。銀行業の根幹を為す預貯金や国内外融資、市場取引の決済管理にかかる大規模な基幹系システムの安全な運用管理はもちろんのこと、DX戦略に掲げるグループ全体での新たなビジネス価値の創造や生産性向上の実現に向けて、既存システムの刷新やデジタル人材育成にも重点的に取り組んでいます。
なかでも私の所属するシステムリスク管理班は、当庫が開発・導入・提供するシステムに内在しているリスクの分析・評価支援を行っています。近年は、国内外で大小さまざまなシステムリスクが発生しています。最近国内では基幹システム移行トラブルによる一部商品の出荷停止や、ランサムウェア被害による業務中断および個人情報の漏洩、世界的にはセキュリティ製品の不具合によるWindowsデバイスでの大規模障害が発生するなど、いずれも多数の関係者に影響を及ぼしました。また、足元では生成AIの技術進歩や浸透にともないサイバー攻撃が高度化しています。このような情勢の下、システムリスク管理班は当庫が開発・導入・提供するすべてのシステムについて、適切なセキュリティの確保をサポートしています。
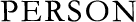 農林中金の人
農林中金の人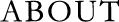 農林中金を知る
農林中金を知る 農林中金が
農林中金が Organization組織概要
Organization組織概要 Recruit site for new graduate
Recruit site for new graduate